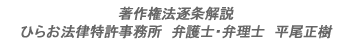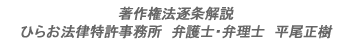|
第2節 著作者(第14条-第16条)
第14条 著作者の推定
著作者とは著作物を創作する者(著作2条Ⅰ②)、すなわち著作物の思想又は感情を創作的に表現した者をいいます。著作者が誰であるかについてしばしば紛争が生じます。その場合は自らが著作者であると主張する者に証明責任がありますが、証明の困難な場合に備えて著作権法は推定規定を設けています。すなわち「著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(実名)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(変名)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者」がその著作物の著作者と推定されます(著作14条)。これはベルヌ条約に基づく規定です。
14条の推定をうける者は、著作物の原作品に又は著作物の公衆(著作2条Ⅴ)への提供ないし提示の際に、実名又は周知な変名が著作者名として通常の方法で表示されている者です。つまり、絵画や彫刻等の原作品自体に著作者名として表示されている者、書籍や音楽CDの発売等の著作物の有形的利用(提供)又は演劇や音楽の上演、放送等の著作物の無形的利用(提示)に際して著作者名として表示されている者です。「原作品」にはオリジナルコピーと呼ばれる複製の彫刻製品や版画刷りも含まれます(加戸・逐条講義)。「実名」とは自然人の氏名又は法人の名称(職務著作の場合)をいい、「変名」とは雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるものをいいます。「変名」は周知でなくては推定をうけられません(注1)。「周知」とは、変名によって表示されている実在人を特定できる程度に社会的に認識されている場合をいいます。誰が著作者であるかは対外的な影響がありますので、近親者だけが認識しているだけでは足りず社会的に認識されていることを要します(注2)。
(注1)14条は推定規定ですから、周知ではない変名を表示した著作者も推定をうけられないだけで、自己が著作者であることを立証して著作者としての保護を受けることができます。また、表示されている者が真実の著作者ではないことを立証して推定を覆すこともできます(仏頭部すげ替え事件)。
(注2)著作権の保護期間は著作者の死後50年間が原則ですが、変名著作物のときは著作者(したがってその死亡時期)が判らない場合がありますので保護期間は公表後50年間とし、ただ周知な変名であれば著作者が判りますので原則に戻って著作者の死後50年間とされます(著作52条)。そして保護期間は独占権の期間であって対外的な影響がありますので、著作権法52条の「周知」は死亡時期が社会的に分る程度に社会的に認識されている意味です。そして、14条によって著作者と推定されると、推定される著作者がいる以上保護期間の関係では公表時ではなく著作者の死亡時を基準とすべきです。ここより、14条の「周知」も52条の「周知」と同様に解するべきです。
「通常の方法で表示」とは、書籍の表紙や奥付、レコードのラベルやジャケット、放送におけるアナウンスやテロップ(以上加戸・逐条講義)、演劇のポスター、パンフレット等に著作者と認識される方法で表示することをいいます(ミュージカル脚本事件)。「著作者名として」表示されなくてはなりません。「出版元」の表示は出版主体の表示であって著作者名の表示ではなく(岡山地判平3・8・27)、映画広告中の「原作者」の表示は映画の原作品の著作者の表示であって、映画の主題歌の作詞作曲者の表示ではありません(籠の鳥事件)。「c」は著作権(Copyright)表示であるから著作者表示にはあたらないとの見解(加戸・逐条講義)もありますが、著作者は原始的著作権者であって、両者は厳密に区別されない場合もありますのでケースバイケースだと思います。
実名登録にも著作者推定効がありますが(著作75条Ⅲ)、原作品や複製物に表示されている著作者名と別の者が実名登録されている場合はどちらの推定が優先するのでしょうか。登録簿より原作品や複製物の方が真実の著作者のアクセス可能性が高いことを理由に14条の推定が優先するとする見解もありますが(田村概説402頁)、14条も75条3項も単なる推定規定ですから、このような場合はどちらかの推定が優先するというのではなく当事者の主張立証によって著作者を決定すべきです(つまりどちらの推定も優先しない)。同一の著作物について別々の者が14条の著作者名表示をしているときも同様です。
第15条 職務著作
1 趣旨
職務著作とは、①法人等の使用者の発意に基づき、②法人等の業務に従事する者が職務上作成し、③法人等が自己の著作名義下に公表する(プログラム著作物では不要)著作物をいい、④法人等と従業者との間の契約や勤務規則で別段の定めのない限り、原則として法人等がその著作者(したがって原始的著作権者も)とされます(著作15条)。平たく言えば、会社の従業員が職務上作成した著作物の著作者は会社であるとするものです。その趣旨は、第一に、法人等の従業者がなした著作は法人等のオフィスや設備を使用し、法人等から対価を得て、法人等の命令、指示、監督の下に行われるのですから、法人等を著作者とすることが妥当であるという点にあり、第二に、このような著作物は多数の従業者が種々の態様で関与している場合も多く、各従業者の寄与を分離しにくく、また各従業者の意思に照らしても法人等を著作者とすることが実態に合致しているという点にあり、第三に、著作物の公表は法人名でなされるのが一般ですから、著作者(したがって原始的著作権者)を法人としておかないと第三者において著作者(著作権者)を推知できないという点です(注1)。
(注1)特許等産業財産権法においては職務発明の発明者は原則として発明者個人であるとされます(特許35条、新案11条、意匠5条)。普通に考えると、産業財たる特許等においては使用者が発明者とされ、文化財たる著作権においては著作者個人が著作者であるとする方が合理的だと思うのですが、法律は逆に規定しています。その理由として、産業財産権法では登録制度を採用していて登録原簿によって権利者を公示できることがあります。次に、産業財産権法では、原則として従業者等が発明者等とされるものの、法人等がその特許権について通常実施権を有するものとして法人等の実施を確保し、また法人等との間の契約、勤務規則等によって、法人等が相当の対価を支払うことによって特許等をうける権利もしくは特許権等を承継できる(予約承継)こととしており、現実にはほとんどの企業が予約承継によって特許権等を承継しています。このことはそもそも職務創作の場合は法人等に権利を帰属させることが妥当であるという実務感覚を示しています。ところで、職務著作は組織的、協働的になされるものばかりとは限らず、特定の従業者個人の才能や力量に大きく依存するものもあり、このようなときは従業者等に権利を帰属させることが妥当かもしれません。しかし、著作権法はそういう職務著作も含めて法人等に権利が帰属し、従業者等と法人等との間の勤務規則や契約で個別に調整することとされています。ただし、産業財産権法のように法人等から従業者等に対する対価の支払いを規定してはいません。
2 要件
職務著作と認められるための要件は次のとおりです。
(1)法人その他の使用者(法人等)の発意に基づくこと
(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること
(3)その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること(プログラム著作物では不要)
(4)契約・勤務規則等に別段の定めのないこと
職務著作は、著作物の創作者が著作者である(著作2条Ⅰ②)とする著作権法の大原則を修正して、創作活動を全くしていない法人等を著作者(原始的著作権者)とする制度ですから、法人等を著作者としてこれに著作者人格権を与え、かつこれを著作権者として著作権を与えることが妥当であるという場合でなくてはなりません。以下、その要件を検討します。
「使用者」とは、法人(権利能力なき社団・財団を含む・著作2条Ⅵ)のみではなく個人営業主も含みます。使用者の「発意」とは、使用者が「こういうものを創作しなさい」と命じた場合に限らず、雇用契約にたつ従業者が勤務時間内に自発的に創作したものであっても、法人等の業務と関連を有し且つ使用者の意図に反しない場合はこれに該当します(北見工業大学事件)。ただし、著作者が法人等と委任契約や請負契約にたつときは、法人等との関係が雇用契約ほど密接ではありませんので法人等が具体的に指示しない限りは「法人等の発意」にあたらないでしょう。
「法人等の業務に従事する者」に関して、RGBアドベンチャー事件の最高裁判決は、法人と著作者の関係を形式的にみるのではなく実質的にみて、「法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払い方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して、判断すべきもの」としており、妥当です。著作活動を行っていない法人等に著作者人格権及び著作権が帰属するのは、著作者が法人等から対価を得て、法人等の指揮の下に、法人等のために著作を行ったという実態がある場合です。そこで、著作者と法人等との関係は典型的には雇用契約(正規従業員に限らずアルバイトやパートタイマーも含む)ですが、会社の役員のような委任契約にたつ者であっても(神聖館開運暦事件 写真で見る首里城事件。ただし、後者は著作者は取締役兼従業者であったから雇用関係にあったとして15条を適用しています)、雇用契約のない学習塾の講師であっても(四谷大塚進学教室事件)、指揮監督下にあって労務を提供していれば該当します。労働者派遣事業法に基づく派遣労働者は、派遣元と雇傭関係にたち派遣先とは雇用関係にたちませんが、派遣先から具体的な指揮命令をうけて派遣先のために労務を提供し、報酬の実質的提供者も派遣先ですから「業務に従事する者」に含まれるでしょう。委任契約の場合、SMAP事件ではフリーライターが出版社の「業務に従事する者」にあたるとし、ブランカ事件ではカメラマンにつき、グッドバイキャロル事件では映画製作会社につきいずれもこれに当たらないとしましたが、創作者と法人等との間の契約関係の実態、創作行為の専門性等の特質、当事者の意識、指揮監督の程度、対価の額などを総合的に考慮して、創作者は法人等に従属する者かそれとも法人等と対等な契約当事者であるかを判断することとなります。なお、対価の支払いがないとき、著作物からみて非常に僅少額の時は原則として「業務に従事する者」に該当しないとみてよいでしょう(神聖館開運暦事件 ハニックデータサービス事件)。
「職務上作成する」とは、法人等に対する職務の履行としてないしはその関連で作成するの意味です。したがって休日に自宅で作成した場合でも職務を自宅に持ち帰ったものであれば本条に該当しますが、勤務時間内であっても全くプライベートに作成した場合(美術会社の営業マンが勤務時間内に作詞した場合)は該当しません。
「法人等の著作名義の下に公表する」ことが要件となるのは、そのような著作物であってこそ法人を著作者とする合理性があるからであり、また第三者が法人を著作者とみるからです。「公表」は、公衆の要求を満たしうる部数の複製物の頒布ないし公衆への提示が必要です(著作4条)。発行者として法人等が表示されるのでは足りず著作者として法人等が表示されなくてはなりません。また現実に法人等の著作名義で公表されている必要はなく、公表が予定されていればよいし、公表が予定されていなくてもかりに公表するとすれば当然法人名義で公表する性格のものであればよいです(新潟鉄工事件)。新聞社のカメラマンが新聞に載せるためにたくさん写真を撮ったが、そのうち新聞に載ったのは一枚だけであっても、残りの写真も新聞社の著作物になります(加戸・著作権法講義)。公表要件を充足しないとして職務著作を否定した判例に、神聖館開運暦事件、計装士講習資料事件があります。ただし、プログラム著作物については「法人等の著作名義の下に公表する」要件自体が外されています(注1)。
(注1)プログラム以外の著作物であっても、たとえば会社の内部文書とか設計図等専ら社内使用のために作成され全く公表を予定していない著作物があります。また、A社がB社から委託を受けB社に納入するためにA社の従業員に作成させた著作物なども、A社としては公表を予定していません。しかし、このような著作物も職務著作としなくてはなりません。そこで、学説では、本文に述べたように、公表するとすれば当然法人名義で公表する著作物は公表要件を満たすとしていますが、これは公表要件は不要だといっているに等しく、この点のプログラム著作物との相違は相対的なものにすぎません。
以上の要件を全て充足していても、法人等との間の契約、勤務規則等で実際の創作者を著作者とすると定められていればその定めに従います。法人等と創作者との間で個別に取り決めをすることを許容したものであり、この場合は第三者からみると著作者が判明しないこととなりますが創作者と法人間の調整を優先しました。こういった定めがあるときは、著作者は原始的に創作者がなり、法人等から創作者に移転するということではありません(著作者が誰であるかは専ら法律の定めにより、当事者の契約で変更することはできません)。
3 プログラム著作物(著作15条Ⅱ)
プログラムの中には最初から企業秘密としてのみ使用し全く公表(著作4条)を予定していないものがあります(特にソース・プログラムは公表しないのが通常)。また、ソフトハウスが発注者のために作成したその専用プログラムは発注者が使用するだけで公表しません。そうするとこのようなプログラムは職務著作の要件を充たさないために、原則に戻って創作者が著作者となりますが、この結果は妥当とはいえません。そこで著作権法は、プログラム著作物については、職務著作の要件から「法人等が自己の著作の名義の下に公表する」という要件を削っています(プログラム著作物に限らず一般の著作物においても公表要件が必ずしも妥当しないことは上述のとおり)。これにより従業者等のプログラム著作物のほとんどは職務著作となり、法人等が自由に利用、処分しうることとなります。そして、その保護期間も公表を予定しているこれまでの職務著作物と同様、公表されたときは公表後50年間、創作後50年以内に公表されないときは創作後50年とされています(著作53条Ⅲ)。
外注委託によって作成したプログラムの著作者(したがって原始的著作権者)は委託者でしょうか、それとも外注委託先でしょうか。例えばA医療法人が医療事務管理システムを考案し、それのプログラミングをBソフトハウスに委託したとします。その際A医療法人は医療事務管理システムに関するアイデア(アルゴリズム)を考案しており、更に種々の情報やノウハウをBソフトハウスに提供しているところから自分がそのプログラムの著作者、著作権者であると言いたいところです。しかし実際にプログラムを作成したのはBソフトハウスですから、15条の職務著作に該当しない限りでき上ったプログラムの著作者、原始的著作権者はBソフトハウスということになります。Bソフトハウスの側から言えば、たしかにA医療法人からアイデアや種々のノウハウの供与を受けたが、実際にプログラムを作成するためには相当なノウハウの蓄積と創作力が必要でありこれを駆使してプログラムを実際に作成したのは自分であるということになります。そして、この場合の外注委託先を「法人等の業務に従事する者」に当ると考えるのは困難ですから、プログラムの著作者並びに原始的著作権者は外注委託先(Bソフトハウス)であると考えられます。その結果委託者(A医療法人)はでき上ったプログラムを他に販売したり、でき上ったプログラムを基礎としてより有用性の高いプログラムを開発して販売することはできません(単なるデバッグやヴァージョンアップをすることは可能です・著作20Ⅱ③)。他方外注委託先はそのプログラムの著作者でありかつ著作権者なのですから、極端なことを言えばでき上ったプログラムを他の医療法人に販売することも可能です。しかし、委託者が委託先に相当額の対価を支払っていることを考えるとこの結論は必らずしも妥当とはいえません。ここにおいて、プログラム開発委託契約において、必要に応じ著作権が委託先から委託者に移転すること、委託先が著作者人格権を行使しないこと、又は委託先は同一プログラムを他に販売しないことを特約しておかなくてはなりません。このような契約上の縛りをかけておくことがプログラム著作物の場合には特に重要となります。
4 効果
15条の要件を充足する著作物は法人等が著作者となります。その結果、公表権、氏名表示権、同一性保持権の著作者人格権は原始的に法人等に帰属し、著作権も原始的に法人等に帰属します。同一法人の複数の従業者等が関与したときも、それらの共同著作ないし結合著作ではなく法人等の単独著作となります。A社の従業員とB社の従業員が共同で著作したときはA社とB社の共同著作となります。
第16条 映画著作物の著作者
著作者は著作物を創作する者をいいますが(著作2条Ⅰ②)、映画は多数の者が制作に関与しますので、そのうちの誰が著作者になるかの定めをおきました(著作16条)。すなわち、映画著作物の著作者たりうる要件は次のとおりです。
(1)制作、監督、演出、撮影、美術等を担当する者であること
(2)その映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であること
「制作」とは映画のプロデューサーの行為、「監督」は劇場用映画の映画監督の行為、「演出」はテレビ映画におけるディレクターの行為、「撮影」は撮影監督の行為、「美術」は美術監督あるいは特殊撮影監督の行為をそれぞれ念頭に置いて規定されたものとされます(加戸・逐条講義)。俳優は著作隣接権者(実演家)としての保護を受けますが、上記(1)(2)の創作活動を行わない限りは映画の著作者ではありません。演出家は実演家として著作隣接権の保護を受けられますが(著作2条Ⅰ④の実演を演出する者)、映画の演出家のときは著作者となる可能性があります。次に、「全体的形成に創作的に寄与した」とは、映画全体に対するイメージを抱きそれを実現した者といった意味です。カメラ監督、美術監督等も撮影部門や美術部門を統括しただけでは足りず、映画の全体的形成に創作的に寄与しなくては著作者とはなりえません。もとより映画を企画した者、制作費を提供した者等の創作に関与していない者は著作者とはなりえません。判例では、宇宙戦艦ヤマト事件ではプロデューサーを、超時空要塞マクロス事件2では総監督をそれぞれ映画著作物の著作者としています。なお、映画の全体的形成に創作的に寄与した者が複数いる場合は複数の者の共同著作物となります(宇宙戦艦ヤマト事件の控訴審では原作者とプロデューサーの共同著作物として和解しています)。上記(1)(2)の要件を満たす映画の著作者をモダン・オーサーといいます。モダン・オーサーは映画製作者(著作2条Ⅰ⑩)との間で映画製作に参加する契約を結び、映画製作者から報酬をもらって映画制作に従事するのが一般ですが、このように著作者が映画製作者に対して映画制作に参加する約束をしているときは映画の著作権は映画製作者に帰属します(著作29条Ⅰ)。映画はTV放映、DVD化といった二次的利用を予定していますが、著作権を有しないモダン・オーサーはそれら二次的利用に際して著作財産権を行使できず、著作者人格権を行使しうるだけです(注1)。映画著作物においても職務著作規定が適用になりますので、モダン・オーサーが法人等の業務に従事する者であって職務著作の要件を具備しているときは法人等が著作者となり(注2)(著作15条)、その結果著作者人格権も行使できません。
(1)映画会社に著作権が帰属したときは、著作者は著作者人格権中の公表権を行使できません(著作18条Ⅱ③)。
(2)たとえば、映画監督とプロデューサーと美術監督が著作者であってそのうちプロデューサーと美術監督が映画会社の従業員であったという場合は、映画会社と映画監督との共同著作物となります(著作権者は参加約束があれば映画会社です・著作29条Ⅰ)。
次に、著作権法は、映画において翻案された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は映画自体の著作者ではないことを規定しています(もとよりこれらの者が上記(1)(2)の創作行為を行ったときは別論です)。この小説、脚本、音楽等の著作者をクラシカル・オーサーといいます。クラシカル・オーサーに二種類あります。一は映画において翻案されている小説、脚本、シナリオ等の著作者です。例えば三島由紀夫の「金閣寺」を映画化した場合であれば、原作小説の著作者である三島由紀夫及びその脚本家やシナリオライターです。二は映画において複製されている音楽、美術等の著作物(映画のBGMとして流された音楽や映画に利用された美術作品)の著作者です。これらの著作者は映画自体の著作者とはなりえませんが、映画のために創作した脚本や音楽等であっても、その著作権は脚本家や作曲家、作詞家のもとにとどまり映画製作者に帰属することはありません。したがって、一の小説家、脚本家、シナリオライター等は、二次的著作物たる映画の原著作物の著作者として映画の著作権者と同一種類の権利を専有します(著作28条)。二の音楽家や美術家等であれば、映画の構成素材である音楽や美術の上映権(著作22条の2)、頒布権(著作26条Ⅱ)を専有し、その音楽や美術が映画と切り離せないときは映画自体の上映権、頒布権に等しい効果をもちます。このようにクラシカル・オーサーは映画の二次的利用に際しても権利が行使でき、二次的利用に関してはモダン・オーサーと比較して保護が厚いといえます。ただし、映画著作物の著作権が保護期間の経過によって消滅したときは、小説、脚本、音楽等の著作権の保護期間が経過していなくても映画の利用に対してはそれらの権利を行使できません(著作54条Ⅱ)。映画と離れた局面では権利を行使できること勿論です。

|